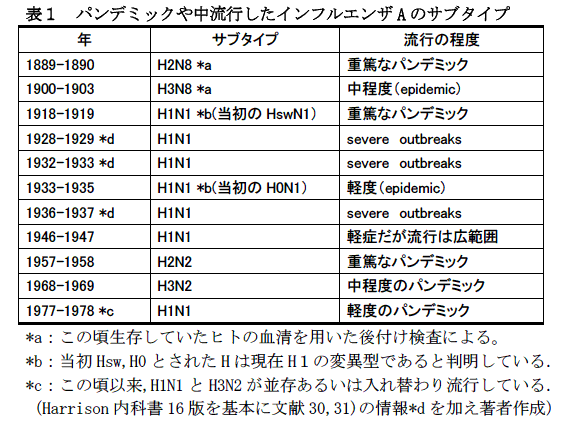
当初、「豚インフルエンザ」−「豚由来新型インフルエンザ」などと呼ばれ、パンデミック直前の状態だと、世界中で大騒ぎになっている。WHOの情報1)よると、2009年5月23日午後3時(日本時間)現在、世界中の43カ国で12,022人の「新型インフルエンザA(H1N1)」感染が報告されており、アメリカ(6,552)、メキシコ(3,892)、カナダ(719)、日本(321)などがその多くを占めている。死亡者数はメキシコ75人、アメリカ9人、カナダ・コスタリカ各1人の合計86人である。死亡率は、メキシコ1.9%、メキシコ以外の中南米0.6%(1/168)、米国0.14%。米国、中南米以外の地域では、0.07%(1/1,397)である。
最近2週間(5月9日から5月23日)で、感染者数は約3.5倍、死亡者数は約80%増加した。日本では大阪府や兵庫県を中心に確定患者数が急増しているが(23日現在で321人)、24日から25日にかけては新患者数は減少してきている。低病原性であることから、精密検査を手控える傾向が出てきているが、精密検査を徹底すれば潜在患者数はさらに多数に上ると思われる。日本の水際防止という名の厳戒態勢、国内の感染拡大に伴うすべての学校の休校や集会、旅行の中止など、無意味かつ異様であった。
外国メディア(ニューヨークタイムズ電子版)2)からは「パラノイア(偏執狂)の国」と呼ばれているほどである。
ようやく一時の狂騒状態は脱しつつあるものの、「新型インフルエンザの世界的流行−パンデミックが来る」ことを前提に、いまだに世の中は回っている。マスメディアに出る専門家は、スペインかぜのときの類似性を根拠に、「第1波は低病原性(弱毒性)でも、秋からの第2波では高病原性に変異したウイルスでパンデミックが起きるかもしれない」と、ほとんど本気で述べている。
しかし筆者は、「パンデミックは起きない」「万が一流行したとしても、スペインかぜのように多数が死亡することはない」と主張してきている3,4)。また、筆者は当初より60歳以上の罹患が少ないことから、今回のインフルエンザウイルスは、「豚(由来)インフルエンザ」でも、「新型」でもない」と考え、2009A/H1N1」と呼んできた4)が、このほど、CDCの調査結果5)から、これが明瞭となった(後述)。
基本的な考え方は、鳥インフルエンザからのパンデミックの可能性に言及した先の論文に記載したが、ほぼ2009A/H1N1の状況が判明したので、改めて今回の「パンデミック騒ぎ」についての考えを述べ、問題点を指摘する。
なお、CDCは、タミフルの使用を発症48時間以降も有効かのように推奨し6,7)、1歳未満の乳児6)や妊婦に対しても制限せず7)、あるいは推奨するように変更した6,8)。日本産婦人科医会は、これを踏襲し妊婦への使用を推奨する通知を会員に対して行った9)。そこで妊婦への使用の危険性について、速報版No119、No120で警告した10-a,b)。1歳未満が特に危険であることは、これまで繰り返し述べてきた通りである。
非ステロイド抗炎症剤(NSAIDs)を感染症の解熱に用いた際の害は、ライ症候群に対するアスピリンの害よりさらに強いと考えられ、TIP誌11-23)および『薬のチェックは命のチェック』24-27)などで強調してきた。また、多臓器不全に注目し、筆者は「敗血症-多臓器不全症候群」、あるいは、ショックに注目して「敗血症-多臓器不全ショック」とも呼んでいる28)。世界的にみても、ライ症候群に対するアスピリンの害の経験、多数の動物実験の成績23,25-27)が、多数の疫学調査の結果23,25-27)がありながら、NSAIDs全体の害としては、世界的にも、ほとんど全く触れられていない。
インフルエンザだけでなく通常のかぜでも非ステロイド抗炎症剤(NSAIDs)を解熱剤として使用することで死亡の危険が高まるという事実は、インフルエンザのパンデミックとの関係でも、完全に無視されている。
ライ症候群や、いわゆる「インフルエンザ脳症」は、インフルエンザなどウイルス感染症において、何らかの原因でサイトカインストームが生じ、ウイルス感染による「敗血症」が重症化し、脳、肝臓、肺、心筋、腎臓などに多臓器不全を生じた病態、すなわち「敗血症-臓器不全症候群」「敗血症-敗血症性ショック」などとも呼ばれる病態に陥ったものといえる28)。タミフルは、こうしたインフルエンザの重症化の防止には無効であり29)、感染予防にも役立たないが、害は一定の割合で確実に生じる。
ところが、一般的な認識は、「軽度の精神神経症状が生じることがある」という程度であり、重症化を防止しないことについてはもちろん、突然死や、統合失調症と区別のつかないような重篤な精神障害、胎児や新生児への害についても、ほとんど何も語られないまま、何の根拠もなく、広く解禁されてしまった。
今回の2009A/H1N1の性質、パンデミックが心配されている鳥インフルエンザ、高病原性の本質とNSAIDsやタミフルの働きを考察し、「パンデミック妄想」への警鐘とする。
今回問題となっている2009A/H1N1は、当初、豚から人、人から人へ感染したインフルエンザウイルスといわれていたが、季節性のインフルエンザの平均約4分の1を占めるAソ連型インフルエンザウイルス(H1N1)と同じタイプである。
1918年H1N1や、大流行にはならなかったが1976年のH1N1も、当初は豚インフルエンザ由来といわれていたが、後にH1N1の変異であることがわかった[30,31](表1)。
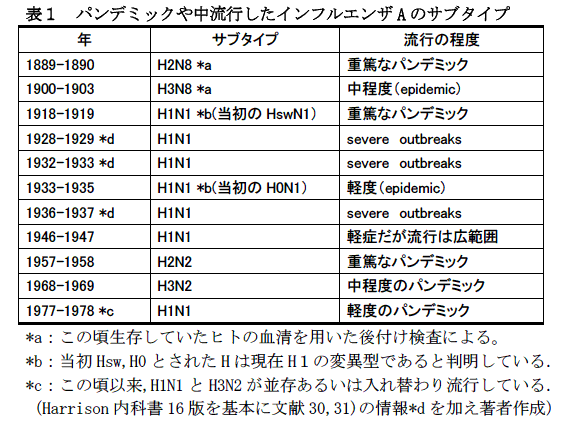
当初から、2009A/H1N1ウイルスには60歳以上の高齢者はほとんどかかっていないのが特徴であったため、どうやら以前に流行したH1N1と似ているのではないかと考えられてきた。1957年にA/H2N2ウイルスによるインフルエンザ(アジアかぜ)が流行するまでは、1918年から1956年にかけては、A/H1N1のみが流行してきた。途中で、1918年〜1945年までとはかなり異なるH1N1ウイルスが1946年から1947年に流行するなど多少の変遷はあったものの、一貫してA/H1N1であった(表1)30,32)。1947年の流行は、流行の地域的な広がりは、パンデミックといえるほど広かったが、死亡率は比較的低かった。
2009A/H1N1ウイルスが1956年までに流行を繰り返してきたA/H1N1と類似したものであれば、1956年以前に生まれていた現在53歳以上の多くの人は感染し免疫を持っている。この免疫は、単にHAやNAに対する抗体だけというわけではなく、感染防御システム全体による免疫と言う意味である。しかし、ある人の血液中に、2009A/H1N1ウイルスのHAの凝集能を阻止する抗体を有しているなら、生後間もなくの頃に罹患したインフルエンザウイルスが、2009A/H1N1に極めて類似したウイルスであったということが分かる。
一般に、人は、生後初めて感染したインフルエンザウイルスに対する免疫が形成され、それと類似のウイルスが流行した場合には、最初に罹患した免疫が呼び覚まされる。インフルエンザウイルスのように、類似しているが、異なるウイルスに変異した場合には、初感染した時の免疫が呼び覚まされても、新たなウイルスの感染を防御できない場合がある。この現象は、(初感染)抗原原罪原理(doctrin of original antigen sin) 33)として説明されている。
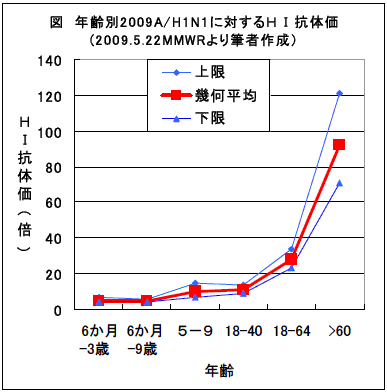
図1に、5月22日にCDCがMMWR34)に発表した年齢別、平均(幾何平均)抗体価の結果を示す。
40歳まではほとんど抗体価は低値であり、18〜64歳のところでやや高値、60歳で著しく高値である。18〜40歳までより18〜64歳のところでやや高値であるのは、40歳超、とくに50歳から60歳超の人にやや高い抗体価の人がいたからであろう。
60歳超の人が人生の最初の頃に、2009A/H1N1と極めて類似したインフルエンザウイルスに罹患していたということは、きわめて明瞭である。
したがって、今回、[豚][新型]インフルエンザと騒がれた原因となったウイルスは、新型でも豚型でもなく、全く通常の人A/H1N1インフルエンザウイルスであると断定できる。
なお、豚インフルエンザは人インフルエンザと共通性が高い。1万年以上前から家畜化されたためと考えられる。また鳥と異なり、行動範囲が狭い。ニワトリは飼育されていても、外から飛んで来た鳥から感染する機会があるが、豚にはそうした機会はない。むしろ、もっぱら人から感染するといってもよい。
豚が鳥インフルエンザウイルスにも感染し、豚の体内で交じり合って新しいタイプのインフルエンザウイルスができるというのが定説のようになっているが、実は、これには強い異論があり35)、この仮説そのものの信憑性が問われている。しかも、豚も人と同様、基本的にH5には感染しない36)。
さらに、人型ウイルスは変異が極めて激しいのだが、豚型ウイルスは、人インフルエンザウイルスと異なり、変異がきわめて少ないとされている。
今回も、豚から人へ感染というより、人のインフルエンザウイルスが豚にも時々感染すると考えるべきものであろう。
これだけの事実からも、今回のウイルスは「新型」や「豚型」と騒ぐのは全く見当違いであり、スペインかぜの時のようなパンデミックには絶対にならないと言える。しかし、それでも国も学者も「新型」とあおった手前か、これを記している24日現在、名称も基本的対策もまだ変更していないし、世界的にみても、「今は低病原性でも、秋からの第2波では高病原性に変異するかもしれないから油断できない」被害者が多数出るパンデミックの恐怖を煽る論調は一向に下火にならない。
しかし、パンデミックは来ない。次の前提がきちんと守られるなら、少なくとも、スペインかぜのときはもちろん1957年や68年の時のような多数が死亡するパンデミックにはならない。
多数の犠牲者を出さないための前提は、(1)NSAIDsを解熱剤として使わないこと、(2)タミフルを使わないこと、(3)実験室から高病原性ウイルスを出さないことである。
非ステロイド抗炎症剤(NSAIDs)、とくにアスピリンやジクロフェナク、メフェナム酸は小児のインフルエンザには原則禁忌となっている。しかし、イブプロフェンが世界的に小児に適応とされ、大人にはアスピリンはもちろん、ジクロフェナクなど多くのNSAIDsが外国でも用いられている。ジクロフェナクが解熱目的で市販薬として販売されている国も中南米や東南アジアなど少なくないことが最近改めて調べてみてわかった37)。
小児に対するアスピリンの危険性は世界の常識となっているが、感染症に対するアスピリン以外のNSAIDsの危険性、大人へのアスピリンも含めたNSAIDsの危険性はパンデミックの議論から全く欠落している38)。最新のWHO情報39)でも、小児にアスピリンを使用しないことは、述べられているが、成人に対する制限はない。
このWHO情報39)では、年齢別の症例死亡率が出ている。小児(19歳以下)の死亡率が0.5%(10/1989)に対して、20歳以上は2.8%(21/754)、30〜49歳は4.0%(29/719)、50歳以上は5.6%(14/251)、成人全体で3.7%(64/1724)と、小児に比較して成人の死亡率が顕著に高い(オッズ比7.6、95%信頼区間3.9-14.9、p=0.0000000)。死亡者は、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)や肝障害、CK上昇、横紋筋融解、腎不全、ショックなど、典型的は敗血症-多臓器不全、ショックを呈して死亡している。成人にアスピリンなどNSAIDsが使用されていたなら生じうる典型的な、敗血症-多臓器不全型ショック症候群である。
小児だけでなく大人も使わないこと。アスピリンやジクロフェナクだけでなく、イブプロフェンやロキソプロフェン、スルピリンなど他のNSAIDsも用いないことが、たとえ流行が大きくなっても大きな被害を出さないための大前提である(詳細は後述)。
WHOでは、タミフルをはじめノイラミニダーゼ阻害剤の備蓄をさらに推奨するという愚行をし、各国は無批判にこれに追随し、さらに2009A/H1N1流行の機会に、何の根拠もなく広範囲に解禁した。しかし、タミフルは、治療に用いても重症化を予防せず、新たな感染も予防しない。そして、重大な害は確実にある。治療・予防に用いないことを前提とする(詳細は後述)。
鳥インフルエンザの高病原性遺伝子を人型インフルエンザウイルスに組み込み、豚を用いてその高病原性を確認する実験がなされている。後述するように、特に、サイトカインの攻撃を免れるNS1遺伝子を有するウイルスが実験室から持ち出される危険性は否定できない3)。万が一、持ち出され、前項1および2と組み合わされるのが、現実的には最も危険である。
このような、最強の高病原性ウイルスが実験室から持ち出されないことも、大きな前提の一つである。
残念ながら、現在の世界の状況では、上記前提が守られているようには思えない。現在は、普段健康な人からも死亡者が出る可能性のある状況である。しかし、これらの前提が完全に守られれば、パンデミックが生じても多数の犠牲者は出ない、と断言できる。
多数の犠牲者が出るようなパンデミックが生じない理由の詳細3)は、『薬のチェックは命のチェック』速報版No1184)で、すでに紹介した。ここではその概略を述べる。
インフルエンウイルスは宿主細胞とシアル酸(sialic acid:SA:ノイラミン酸)で結合するが、鳥と人とでは、シアル酸が立体異性体の関係にあり、そのため、細胞のガラクトース(レセプター)と結合する部位は鳥と人では異なる36)。鳥では、たとえば、アヒルの腸粘膜上皮細胞に含まれているのは大部分がSAα2,3ガラクトースであり36)、ガラクトースの3位の炭素とシアル酸の2位の炭素がα2,3結合をする。一方、人の気管支粘膜上皮細胞に含まれるのは大部分がSAα2,6ガラクトースであるため、人ではガラクトースの6位の炭素とシアル酸の2位の炭素がα2,6結合をする36)。ただし、絶対ではないため例外はありうる36)。
香港での養鶏業者の調査や、ベトナムでの鳥インフルエンザ濃厚接触者の調査から、濃厚接触した人の約3%が新たに感染したが、発病はしないか、してもごく軽症であった3,4)。日本でも同様。感染者全体では、死亡率はほとんど0である。発病し死亡するのは極めて特別な場合と考えられる3,4)。
鳥のHは16種類(H1〜H16)が確認されている。鳥類の歴史は1億年以上である。1億年かけて16種類を獲得した。つまり1種類あたり数百万年以上要している。人はホモサピエンスで20〜30万年の歴史。その間に3種類のHができた。1種類あたり数万年以上要している。そうした大変異でH5の高病原性人型インフルエンザができる確率は極めて低い[3,4,27]。
インフルエンザウイルスの失活にはサイトカインが重要である。発熱がピークに達しインターフェロン産生がピークに達するまでにウイルス活性は低下し始めている36)。タミフルの使用を開始する発熱48時間までには、相当減少している。
一方、ライ症候群やインフルエンザ脳症など重症脳症、敗血症性ショック、高病原性鳥インフルエンザ死亡例では、炎症性サイトカインが異常高値となっている。何らかの原因でウイルスがサイトカインの攻撃を免れると、生体内でサイトカインが過剰に産生され、サイトカインストームを来たし、ウイルス疾患は重症化し死亡に至る3,4,26)。
NSAIDsはプロスタグランディンの合成を阻害し、解熱作用、抗炎症作用を発揮する。ウイルスの生存には有利な環境となる。いわばインフルエンザウイルスが、サイトカインによる攻撃を免れ、増殖する一方、TNF-αなど炎症性サイトカインの誘導を増強する。
動物実験では、感染動物の死亡危険を高める。多数の動物実験のメタ解析の結果、統合オッズ比(Petoオッズ比)は7.52であり、その95%信頼区間(CI)は4.58-12.35,p<0.00001)であった26,40)。
また、米国(ライ症候群)でも、日本(脳症)でも、重症脳症や脳症による死亡の危険を有意に高めることが確認されている(オッズ比15〜47)40)。
そして、その危険は、小児だけでなく成人でも同様であり、アスピリンやジクロフェナクに限らず、イブプロフェン、ケトプロフェン、スルピリン、ロキソプロフェンなどあらゆるNSAIDsが関係する26,40)。
1918年のスペインかぜのパンデミックでは、アスピリンが大量に使用された。多くの死亡にアスピリン使用の影響が大きいと考えられる3,4,27)。
ウイルスの高病原性には、HAおよびNA、インフルエンザウイルスの増殖に関係するPB2、非構造タンパクに関係した遺伝子(NS1)、とりわけ、NS1遺伝子が重要である。
香港で流行したH5N1型鳥インフルエンザウイルスのNS1は、インターフェロン(αとγ)やTNF-αの抗ウイルス作用に対して耐性を有していることが確認された。
このNS1遺伝子を人型のH1N1インフルエンザウイルスに組み込み、豚に感染させたところ、感染させられた豚は発病し、著しく長期間、発熱やウイルス血症が続き、重症化した42)。したがって、もしも人がこのウイルスに感染したとすると、やはり重症化する恐れがある。
タミフルは、インフルエンザウイルスのノイラミニダーゼを阻害する。ウイルスの増殖を阻害するわけでも、サイトカインからの攻撃を免れないようにするわけでもない。ただ、呼吸器粘膜からインフルエンザウイルスが離れがたくするだけである。
タミフルの作用点は、高病原性に関係する最重要遺伝子NS1には全く無関係である。したがって、この作用機序を見るだけでも、高病原性ウイルスによるインフルエンザの重症化や、死亡を防止することがあり得ないことであることが分かる。タミフル使用を推奨する横田俊平医師も述べていることである29)。
繰り返し述べられているように、低病原性(弱毒)ウイルスによるインフルエンザは、季節性のインフルエンザと同様であり、タミフルなしで治癒する。そして、高病原性ウイルス感染による重症化を予防しない。
これも繰り返し述べていることだが、タミフルを予防に使うと、検査でインフルエンザウイルスが陽性に出るインフルエンザを有意に減らすが、検査で陰性のインフルエンザ様症状は有意に増える。そして、検査が陰性陽性問わずインフルエンザ様症状(+脱落)を合計すると、全く差がなくなる26,27,41)。
そして、「精神病」など重大な精神障害、高血糖・糖尿病誘発、四肢痛、耳痛、頭痛などが有意に増加する43)。多数の被害者が出た場合、不可逆的となる可能性も否定できない。これだけでも、害/益比の判断は自明である。
CDCや日本産婦人科医会が、妊婦へのタミフルの使用を推奨しているが、妊婦に用いると新生児の死亡が確実に増加しうる44)。また、妊婦自身に重大な害が生じうる44)し、流産や胎児死亡の危険もありうる45)ので、使用すべきではない。
米国カリフォルニアでは、2009A/H1N1ウイルスに罹患した妊婦5人中1人が(タミフル服用の有無は不明であるが)流産している46)。
先述した3つの前提を厳守すればパンデミックは起きないし、万が一起きたとしてもタミフルは役立たないと断言できる。
なお、人の免疫システムは極めて巧妙であり、今のところ、NS1を人イルスに組み込み豚で実験した関係者らから重症感染者が出たとの報告はない。種々の防御システムが働くからであろう。
60歳以上の人は、2009A/H1N1のHI抗体を高率に保有している。したがって、2009A/H1N1ウイルスは、1956年以前に流行したインフルエンザウイルスと極めてよく似た季節性インフルエンザウイルスであり、低病原性(弱毒性)ウイルスである。
死亡しているのは、もともと合併症などのある人である。したがって、この点からも、通常のインフルエンザ並みである。
メキシコでの死亡者が多い点に関して、貧困と、医療保険未加入者が50%と多いこと、そのため市販薬に頼り47)、医療機関への受診が遅れるケースがあることが指摘されている47,48)。そして、市販の非ステロイド抗炎症剤が解熱剤として売られている(イブプロフェンやジクロフェナクなど)ので、使用されているかもしれない。
米国で罹患し入院した感染者の約半数にタミフルが用いられているが、カナダではわずか6%である39)。タミフルが用いられなくとも大部分が回復している。いずれにしても、NSAIDsを大量に用いなければ犠牲者が多数出るパンデミックにならない。
NSAIDsを解熱剤として用いない限り、多数の犠牲者が出るようなパンデミックはもはや起きないと考える。小児だけでなく成人にも使用してはならない。また、ステロイドもパルス療法を含めて使用しないことである。これらNSAIDsやステロド剤を解熱目的で使用すると、一時的には症状は軽快したとしても、その後に高サイトカイン血症を起こしてかえって重症化する危険性が高い。
抗ヒスタミン剤なども無効であり、痙攣の頻度を高める49)ので、用いるべきでない。余分な薬剤を用いず、保温と安静を保ち、患者の免疫力が最大限に発揮されるよう配慮することが肝要である。そうすれば重篤化や死亡増大の危険性はない。したがって、医療従事者自身が恐怖におびえるという必要はまったくない。国にもマスメディアにも過剰な反応を謹んで頂き、真に危険なNSAIDsの使用を厳に慎むよう情報を発信していただきたい。