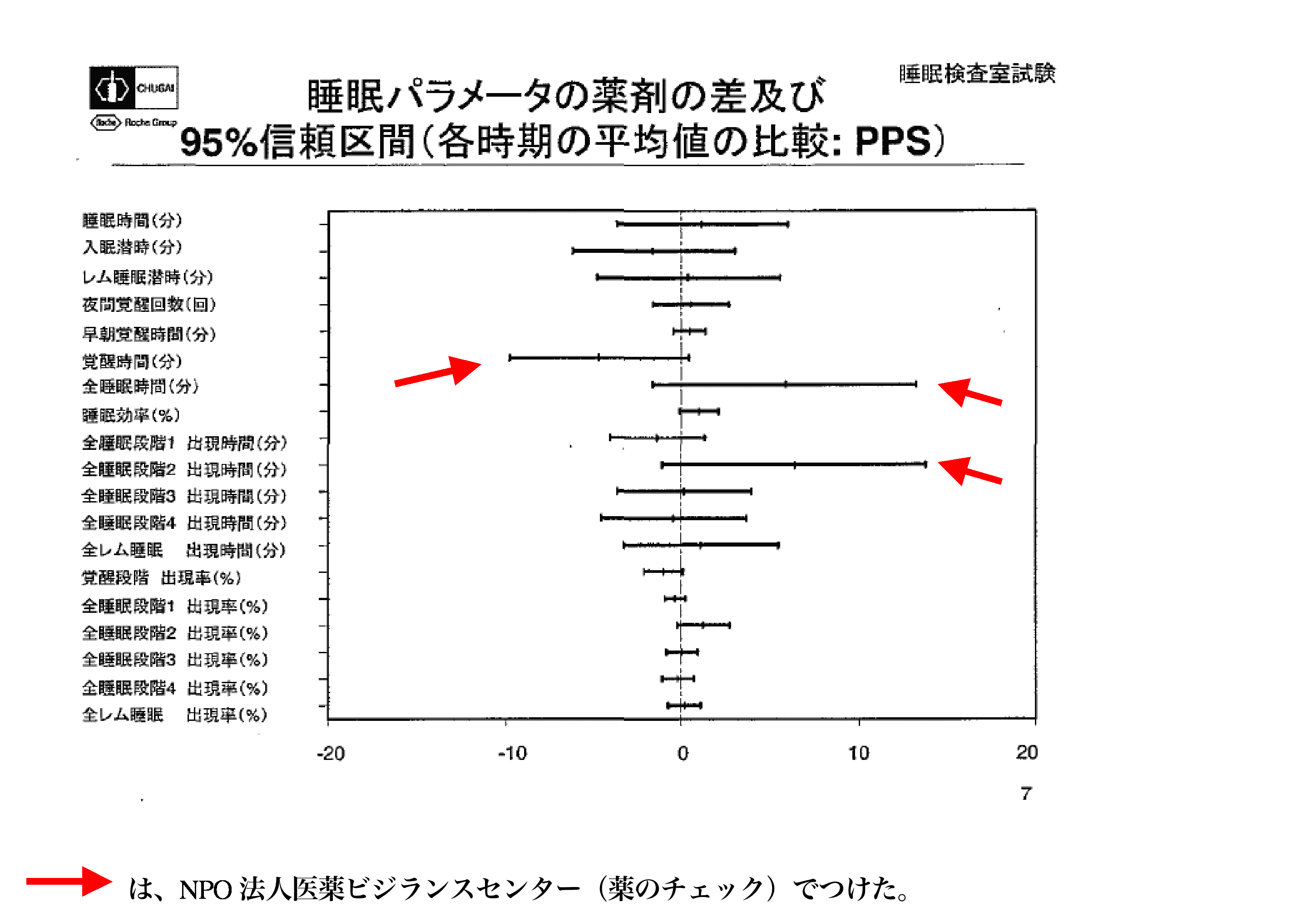『薬のチェックは命のチェック』インターネット速報版No98タミフルの害:作業班に開示された情報は因果関係を示唆する
64倍のデータはこちら
<中外の報告>
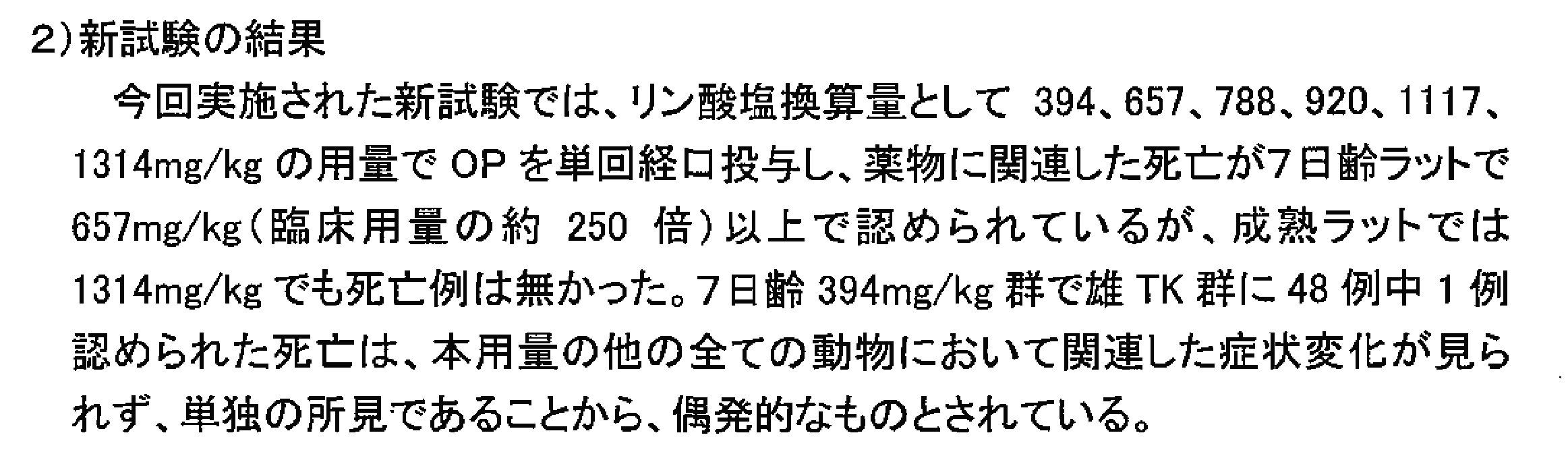
このデータの開示を求めたが、中外製薬は拒否しているため、検証できない
直接脳室内に投与脳中平均濃度:最高926ng/mL(ng/g)=0.926μg/g 突然死用量(OT1000mg/kg)で死ななかったラットの脳中最高濃度=45μg/g したがって0.926μg/gは,その約50分の1という低い濃度に過ぎません。 これでは行動に変化が生じなくて当然です。
長期曝露では、臨床治療量の1.6倍超で阻害の可能性あり
タミフルは、活性体になって、インフルエンザウイルスのノイラミニダーゼを 阻害して抗ウイルス活性を発揮 するといわれています。ノイラミニダーゼは、ヒトも含めて、哺乳類のあらゆる細胞にあるのです。 細胞が若さを保つために必要な酵素です。
- ノイラミニダーゼには現在4種類が見つかっています。
- NUE1=ライソゾームノイラミニダーゼ. NEU2=細胞質ノイラミニダーゼ
- NEU3=ミトコンドリアノイラミニダーゼ, NEU4=細胞膜ノイラミニダーゼ
- メーカーの実験では、1ミリモル濃度(mMと表します)までノイラミニダーゼを 阻害しなかったと言っています(ただし、曝露時間は示していません。 おそらく短時間しか作用させていないと思われます)。
- 1匹が死亡した14日齢ラットの未変化体タミフル(OT)1000mg/kg群の生存ラットの、 活性体タミフル(OC)の平均血中濃度は132μg/mL=モル濃度換算で約0.5mM(ミリモル) これは、NEU1−4の非阻害濃度(1mM)のたかだか2分の1に過ぎません。 つまり,短時間曝露では致死用量近くでノイラミニダーゼが阻害されるということです。
- ラット2年間のがん原性試験では、ヒトの臨床治療量のたかだか1.6倍超で発がんの可能性があり、 これはヒトのノイラミニダーゼが阻害された結果であると考えられますが、 この時の濃度は1mMの150分の1でした。つまり、長時間タミフルに曝露されると、 おそらく短時間曝露での阻害濃度1mM超の150分の1超で阻害されうると考えられました。
- しかし、これらの点について、WGでは何も考察をしていません。
メーカーは、中枢作用や不整脈に関係する、重要な標的 (受容体やイオンチャネル、酵素など)を157種類調べた結果、30μMまで活性を示さなかったので、 中枢作用などはない、と結論付けています。
しかし、タミフルの毒性の特徴である突然死や異常行動は、睡眠剤や鎮静剤、 抗不安剤、抗けいれん剤であるバルビタール剤やベンゾジアゼピン剤の作用とそっくりです。 これらの薬剤が作用するのは、ベンゾジアゼピン受容体ですから、 タミフルがベンゾジアゼピン受容体に作用するかどうかを調べるだけでも有用なくらい重要な受容体です。
これが調べられていないのでは受容体をなにも調べていないのと同じです。
157種類の受容体などを調べてベンゾジアゼピン受容体は調べていない。
明瞭な結果が出るはずの実験(感染、受容体)は実施せず
と、最初に言ったのはこのことです。
インフルエンザにかかって発熱したときにこそ、血液-脳関門が障害されてタミフル (未変化体)が脳中に高濃度に移行すると考えられますから、 動物にウイルスなどを感染させて実験すれば、離乳前のラットが呼吸抑制で死亡したのと 同じ現象が成熟した動物でも再現されるはずです。
NPO法人医薬ビジランスセンター(薬のチェック)では、 その実験の重要性を以前から提案してきました (『薬のチェック』速報No82)。 当初基礎WGでも、メーカーに指示したのですが、メーカーの都合で取り下げられました。
明瞭な結果が出るはずの実験(感染、受容体)は実施せず
といったのはこのことです。