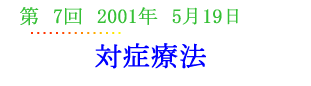
![]()
熱が出たら解熱剤、痛みに鎮痛剤、咳に咳止めというように、病気の不快な症状を和らげる治療法を「対症療法」という。
治療にはほかに、病気原因を取り除く「原因療法」と、本来あるものがなくなったり不十分になった時に補う「補充療法」がある。例えば、前者は結核に対する抗結核剤。後者は、糖尿病に対するインシュリンだ。
理想はもちろん原因療法。でも、残念ながら、そのような治療法はそれほど多くない。多くは対症療法か補充療法だ。
対象療法は、痛み、熱、下痢、咳、痰、鼻水、動悸、息切れ、呼吸困難、震え、かゆみ、発疹、めまいなどあらゆる症状が対象になる。
中でも、最も耐えがたいのは「痛み」だ。ありとあらゆる臓器で痛みが生じる。頭痛、目痛、鼻痛、歯痛、神経痛、骨の痛み、喉の痛み、狭心症や心筋梗塞の痛み、腹痛、生理痛、帯状疱疹の痛み、ガンの痛み・・・。どの科の医師も、痛み止めの対症療法に習熟しておかなければならない。これがきちんとできないようでは、患者に責任ある治療を行なったことにならないくらいだ。
でも、対症療法には、充分な注意が必要だ。症状を抑えるだけで、本来の病気に悪影響がない場合はよいが、元の病気を悪くする事がしばしばあるからだ。
多くの症状は、病気の原因を取り除こうとする正常な生体反応の結果である。発熱は、ウィルスや細菌の侵入に反応し、それらの病原体を排除しようとすr防衛反応の一つ。下痢や咳も同様だ。その大切な生体反応を抑えてしまう事は、感染症などの原因を取り除くのを遅くしてしまう恐れがある。実際、感染時の解熱剤や下痢止めなどは、多くの場合、完全回復を遅らせることが知られている。
対症療法は、元の病気が悪化しない程度とし、副作用が効果をしのぐ事がないように最小限にする。
これが対症療法の原則だが、例外もある。長く続く痛みは放っておくと別の痛みを誘発して強くなり悪循環になる。特にガンの痛みは、出たらたたく「もぐらたたき」方式ではだめ。痛みが出ないように、十分な量の痛み止めを長期に使うべきだ。
薬の診察室 (朝日新聞家庭欄に2001年4月より連載) 医薬ビジランスセンター
浜 六郎
