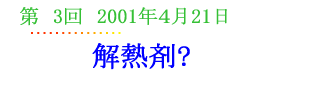
![]()
病気で苦痛なのは、なんといっても熱と痛み。熱はかぜや扁桃炎、肺炎にはつきものだし、がんでも時にはでる。たいていは病気が重いほど熱は高く、痛みも強くなる。病気が治ってくれば熱は下がる。熱の高さは病気の重さの一種のバロメーターだ。
だから、誰しも、早く熱が下がって欲しいと思う。解熱剤で下がったら、病気がよくなったような気になる。
ところが、昔はそうは考えなかった。「医術の父」ヒポクラテスら古代ギリシャでは、感染した時に熱が出るのは有益な兆候とみていた。その後2000年間、この考え方は続いた。たとえば、17世紀のイギリスの医師シデナムは「熱は、自然が与えてくれた外敵に勝つためのエンジン」と書いている。
実際、トカゲでも細菌に感染すると、気温の高い方に移動する。イグアナに細菌を注射して感染させた実験では、外気温を38度にすると4分の3が死んだが、40度では3分の1,42度では全く死ななかった。
様子が違ってきたのは、解熱剤ができてからであるらしい。
解熱剤の誕生は19世紀だ。昔から柳の樹皮などに解熱効果があることは知られていたが、その成分がサリシンとわかったのが1829年。次いで75年、解熱剤としてアスピリンの仲間であるサリチル酸ナトリウムが登場した。その後ピリン系など数々の発見・開発を経て93年、毒性が少ないアセトアミノフェンが登場した。
そして、その6年後アスピリンができる。アスピリンは、熱を下げるだけでなく、リウマチなどの炎症を抑える効果が優れていたため、アセトアミノフェンなどの先輩格の解熱鎮痛剤にとってかわることになった。
歴史的には、本格的な解熱剤が登場してから、まだせいぜい100年余りなのだ。
解熱剤を使うと、高い熱もたちどころに下がる。熱が下がれば一時的には体は楽になったように感じる。このため、熱の効用が忘れられてしまい、解熱剤が善玉に、本来善玉の熱のほうが逆に悪玉の汚名を着せられる羽目になったのである。
欧米でも、「かぜをひいて熱が出たら、アスピリンを飲んで寝ていればよい」と言われ、解熱剤は善玉=安全と思われてきた。ところが、実は安全ではなかったのである。その話は次回に。
薬の診察室 (朝日新聞家庭欄に2001年4月14日より連載) 医薬ビジランスセンター
浜 六郎