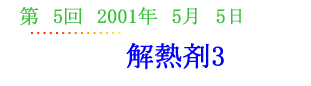
![]()
解熱鎮痛剤は大きく分けて、アセトアミノフェン系と非ステロイド抗炎症剤がある。後者には、アスピリンやジクロフェナク、メフェナム酸が入る。
前者にも害はあるが、後者に比べ圧倒的に安全。どうしてか。鍵を握るのが「炎症」だ。
実は、解熱の仕組み自体は、両者とも同じだ。
延髄には体温を調節するサーモスタットのような装置がある。それを「上昇」に作動させるのが、プロスタグランディンという物質。病原体に感染すると、患部から指令が出て脳の視床下部でのその合成が進み、延髄に「発熱」命令を出す。
どの解熱剤も、この視床下部でのプロスタグランディン合成を抑えるから、体温が下がる。
ただ、アセトアミノフェンはここまでで、限定的に脳にだけ働く。だが、抗炎症剤は文字通り「炎症」した患部だけに働く。
「炎症」にはマイナスイメージがあるかもしれないが、病原体などの外敵を局所に押しとどめ、傷ついた体を修復する大切な生体反応。けがをしたら患部が「赤く」「はれ」「熱」を持ち「痛い」。この4つが特徴だ。
正常な炎症では、しばらくすると患部は軟らかくぶよぶよしてくる。周りに壁ができて中に膿がたまる。これは修復が本格化した証。こうなるともう炎症は広がらない。
この一連の炎症の主役も、プロスタグランディンだ。ここでは血管を広げ、患部へ送り込む血液を増やすように働く。赤くなり痛むのはこのため。血管は、傷ついた組織の再構築に必要な物質の大切な補給路だから、この流れを太くすれば修復ピッチが上がる。
ところが、抗炎症剤は、患部でもプロスタグランディンの合成を妨げる。不快な熱や痛みも一時的に抑えるが、正常な炎症も抑えてしまう。そのため、使うと初めは楽になったように思っても、最近やウィルスが局所を突破して感染も炎症も全身に回り、最終的には傷の治りが遅れ、病気が長引き重くなる。
だから飲むなら、脳だけに働き、修復に必要な炎症反応を損なわないアセトアミノフェンを。ただし、解熱は、エアコンに例えれば、病気だから暖かくと思って高い室温に設定したのに、横から無理に別の人が低く再設定するようなもの。くれぐれも効かせ過ぎにはご注意を。
薬の診察室 (朝日新聞家庭欄に2001年4月より連載) 医薬ビジランスセンター
浜 六郎
