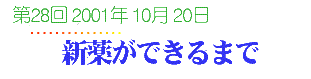
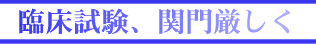
今週は、ちょっと一息入れて、薬が生まれるまでの話を。
薬は体にとっては異物だから、何らかの毒性(危険性)はつきものだ。とはいえ、その危険は許容できる程度であること、つまり危険を上回る利点(症状を和らげ、予防するなど)が必要になる。
いくら効果がありそうな物質でも、毒性が強いものは、いきなり人に試せない。期待する効果が表れる量で、許容できない毒性が表れないことを、まず動物実験で確かめる。
これで一応「安全」なものは臨床試験に進む。一般の診療で使ってよいとのお墨付きを得る登用試験のようなものだ。これには3段階の関門がある。
まず、少数の健康な人を対象に主に安全性を調べる。
次に、少数の患者で効き目の目安をつける。
さらに、数百〜千人を上回る患者を対象にして、厳密な最終試験をして、判定をする。
関門は単に三つあればよいわけではない。有効性は特に厳しい吟味が必要だ。有効であると証明するためには、その物質を使った時と、そうでない時の厳密に公平な比較が欠かせない。特に大切な最終試験で、公平性を保つポイントは四つある。
まず、「候補」の物質を使うグループと、比較相手(理想は偽薬だが既存薬の場合もある)を使うグループとに、対象の患者を公平に分ける。その手続きの基本は厳密なくじ引き法(無作為な割り振り)である。これで、男女の比率や年齢、病気の重さがほぼそろうようになる。
第二に、グループ分け当初の公平さを最後まで保つ。副作用が出て、都合が悪くなった人を途中で除いてはいけない。
第三に、効果や副作用の判定にひいき目が入らないよう、「候補」か比較相手か、どちらが使われたのか、患者にも医師にも分からないようにする。これが「二重目隠し法」だ。
第四に、効力を評価するのに医師の主観ではなく、客観的で意味あるデータで判断する。
日本では、一見、厳しい関門が設けられているが、試験途中で死亡した人を「因果関係が不明」として除くなど、抜け道がいろいろあった。効かない薬、危険な薬を生まないためにも、ぜひ、薬の登用試験そのものにも関心を向けてほしい。
薬の診察室 (朝日新聞家庭欄に2001年4月より連載) 医薬ビジランスセンター
浜 六郎