
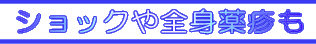
歯科治療で抗生物質注射を受けた東大教授が、ショック死したことがあった。50年代のことだ。大問題となり、ペニシリンなどショックを起こしやすい抗生物質には、過敏さを判定する皮内テストが必要になった。
教授の死因は、アナフィラキシー・ショック。抗生物質や他の薬でもおきる。薬を点滴や内服した後、早ければ数分後に体がかゆくなり、蚊にかまれた時のようにはれ、たちまち全身にひろがる。ゼーゼーと呼吸困難になり、唇が紫に変色。意識を失い、けいれんを起こすこともある。処置を誤れば致命的だ。
細菌は一つ一つ、カプセルのような壁を持ち、自力で代謝し増殖もする。ペニシリンとそれに似たセフェム系など抗生物質の主なものは、この細菌の壁を作らせないように働き、菌を殺す。人にないもの(細菌の壁)を攻撃するため、人には比較的安全だが、異物だから、アレルギーはなくならない。このため、薬疹(やくしん)などは100人中1〜2人に、ショックも1万人に1人程度起きる。2000人に1人起きる抗生物質もある。
一方、ペニシリンやセフェム以外の抗生物質の多くは、細菌が自ら生存・増殖するのに必要なたんぱく質や核酸を作るのを妨げて、効果を発揮する。人の細胞と同様の成分ができないように働くから、これらの抗生物質は菌抑制に必要な量で、人の細胞にも影響しうる。このために、副作用が比較的出やすい。
副作用は抗生物質によって異なるが、結核に使うストレプトマイシンは長期に使うと難聴になることがある。クロラムフェニコールは血液成分が極端に減る重い副作用のために、今はほとんど使われない。テトラサイクリン剤は8歳未満に使うと歯が黄色く着色することがある。なかには、めまいを起こしやすいものもある。本来不要だが、かぜにも使われているキノロン剤は、解熱鎮痛剤との併用で、けいれんを起こすことがある。
抗生物質は病気の原因菌をやっつけてくれる。肺炎、尿路感染、敗血症などの治療には欠かせない。そういった場合は多少の副作用は我慢できる。だが、使う意味のない人には少しの副作用も問題だ。不要時には使わない、これが重い副作用から逃れるために大切だ。抗生物質は「とっておきの薬」と考えて。
薬の診察室 (朝日新聞家庭欄に2001年4月より連載) 医薬ビジランスセンター
浜 六郎