書評コーナー
季刊誌32号より
「母」たちの戦争と平和ー戦争を知らないわたしとあなたに
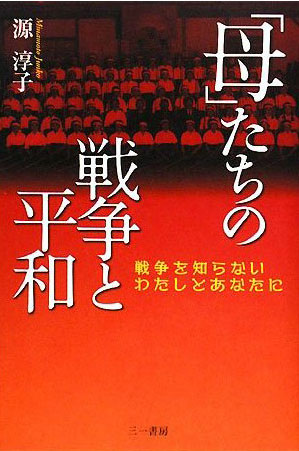
源 淳子:著/三一書房
■19.5×13.5cm 216頁/価格1500円(税別)
私が小さかった頃、晩酌で頬を真っ赤にした父が話し始めるのは、決まって空襲のことでした。学徒動員で働いていた 工場が爆撃されたことなど、繰り返し話してくれました。
本書は、父より少し上の世代の女性4人の聞き取りがベースになっています。軍国少女として軍事教練にいそしんだこと、 疎開児童の引率教師として食料調達に苦労したこと、恋人の戦死、そして敗戦。直接戦場に赴くことはなかったけれど、 それぞれが戦争に組み込まれていました。その4人は、それぞれの「分岐点」から反戦への思いにいたります。
4人の体験を通して感じるのは、戦争中の事実はその時代を生きた市民にきちんと知らされていなかったということ。 「「お上」のいうなりに信じていた…、いまになって恐い時代だったといえるんです」と1人の女性は語っています。 事実を知ることの大切さを再認識した一言です。戦後を生きているつもりが、後に「あの時代は戦前だった」ということも あるでしょう。空襲の話をしてくれた父はもういません。戦争の記憶が急速に薄れつつある今だからこそ、一読の価値ある一冊です。(み)

