書評コーナー
季刊誌35号より
「史上最悪のインフルエンザ〜忘れられたパンデミック」
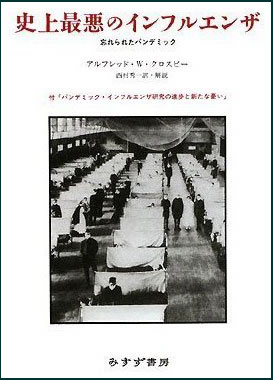
アルフレッド・W・クロスビー著 西村秀一訳/みすず書房
■価格4400円(税別)
本書はもともと1976年にアメリカで出版された本である。俗に“スペインかぜ”と呼ばれている1918年のパンでミック。 それから半世紀を経て、この悲惨な経験がすっかり忘れられているのではないかという警告が込められている。 歴史学者である著者は、当時の膨大な資料をよくぞここまでというくらいにきれいに整理してみせる。 未曾有の世界戦争と疫病の大流行に翻弄されつくした当時の人々の様子がまるで大河ドラマをみるように生き生きと伝わってくる。
当時の医学では、インフルエンザの病原体であるウィルスはまだ発見されていなかった。 このような状況下で、医学界や社会はどのように感染症に対峙したのか。そのありさまを克明に描いた本書を読むと、 そこには現代にも通じる教訓がある。
例えば、パンデミックの原因論争である。当時最も権威があった細菌学者ファイファーは、 すでに“インフルエンザの原因”とされる「桿菌」を見つけ出していた。 もちろんインフルエンザの本当の病原体はウィルスなので、実際にはその「桿菌」が検出されない患者も多数見つかるのだが、 当時「細菌学の巨人」とまで呼ばれていた権威の説であったために、多くの科学者らがそれを信じ、結局、 真相解明が大幅に遅れてしまった。科学者集団といえども、目の前の科学的事実を直視せず、学会の通説や権威の意見に 左右されやすいということが改めてわかる。
訳者の西村秀一氏は、いまの日本のインフルエンザ研究者の中では数少ない、ややまともな(科学的) 意見を主張している学者(医師)である。新装版発行に当たって追記された西村氏による「解説」も、 たいへん読みごたえがある。(隅本邦彦 江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授・元NHK記者)

